| 右、ちょっと珍しい「増髪 」を写してみました。玉鬘なんかに使用すれば良い効果を見せてくれそうな、怪しい雰囲気を持った増髪です。原型は甫閑ですが、特に大胆に太く引かれた毛描が変わっていて、魅力的な面です。金春家にそっくりな型のものがあります。今年の三月の金春の月報の表紙に写真が出ています。 |
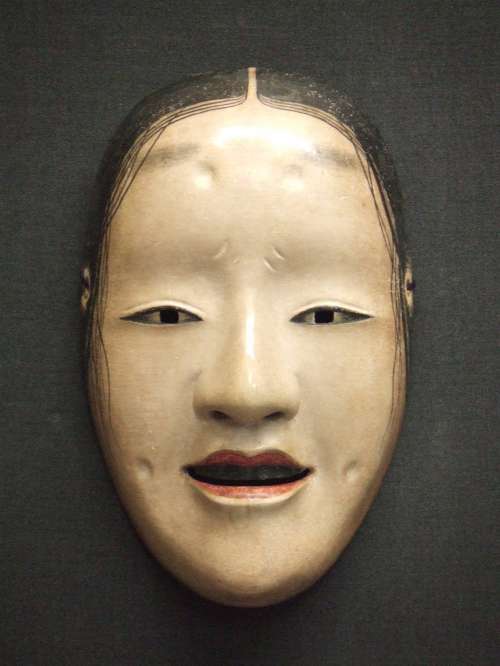 |
平成23年7月17日に、平成22年夏から23年春までの活動のページが消えてしまいました。
バックアップも取っていませんので、復元不可能となっています。
もしも、外套のページをコピーされている方がおられましたら、祐門会の「お問い合わせ」
欄にでも、御連絡頂ければ幸いに存じます。 |
 |
野村祐丞氏・増田秋雄
氏らによる狂言「宗論」
です。絶妙の掛け合い
は 、何時もながらに
見事です。 |
 |
「石橋」前シテは
私の制作の童子
です。 |
 |

赤は私作の「獅子口」 |
 |
大きくて力強い、髙橋親子の迫真の舞台でした。
金沢能楽会・別会能平成22年9月5日
「石橋、連獅子」でした |
|
やっと「長霊癋見」の完成です。
江戸時代初期の出目古元休の作品の写しです。
盗賊らしい髭を蓄えた無骨な表情に、間の抜けた熊坂長範のユーモラスな
表情が混ざっています。長霊癋見は
三度目ですが、毎回毛描をする度に
視力と運動神経の衰えを感じさせられます。2010.8.27 |
 |
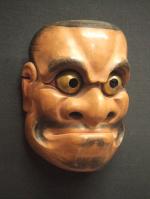 |
 |
 |
2010年金沢能楽会の別会「連獅子」に使用する獅子口の面です。左は彩色をする前で、右は完成写真です。9月の舞台で活躍してくれる事を願うばかりです。
この獅子口の本面は、宝生流の国指定の重要文化財に指定されている、室町時代の本面を写させて頂いたものです。現存する様々な獅子口の型の基になっているものです。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 平成22年11月2日(火)~7日(日)、京都南禅寺にある財団法人野村美術館での、「後藤祐自能面展」の様子です。約35面の展示でした。 |
 |
 |
和倉温泉の旅館、加賀屋の展示ケースにある、祐自作の
「小面」と、「平太」です。平成22年 |
|